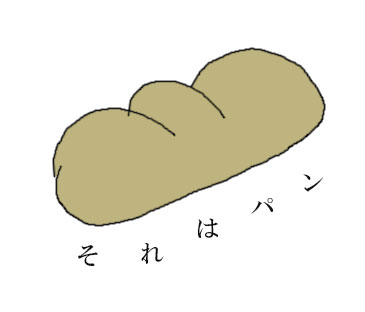当日はあっけなくやってきた。手術は一人三十分で終わるらしい。意外と短い。始まってしまえばトントンと終わる気もする。待つ方が辛いのかもしれないと思った。この病院の執刀医は院長だけなので、三十分ごとに呼ばれるわけだ。僕たちは、この病室で誰が最初に呼ばれるのかで争っていた。
「多分、患者番号が若いほうからだと思う。これ申し込み順でしょ?」
大橋案は納得感があった。そうなると、一番は熊田さんだ。熊田さんは「嫌だよ俺は~! 二番目がいいよ~!」と駄々をこねていた。
大橋さんは手持ち無沙汰なのか、何度も何度もペットボトルを手にして、口に水を含んでいた。
「大橋さん。水飲んで大丈夫ですか?」
腰椎麻酔のあと8時間は下半身を動かすことができないので、トイレも行けないらしい。足が動かないこともそうだのだが、力めないんだそうだ。しかし尿意は脳で感じるので、苦しいことになる。従って、その間に尿意を覚えた場合は尿道カテーテルになるという説明が事前にあった。痛いことは絶対に増やしたくなかったので、僕は朝から水を一滴も飲まなかった。肛門を切られた直後に尿道に管を刺されるなんてどこの国の拷問だろうか。ところが大橋という男が、目の前でゴクゴク水を飲んでいるのだ。僕の発言に大橋さんは一瞬しまったみたいな顔をしたが、小さい声で「大丈夫……」と言ってもう一口飲んだ。小さな大丈夫は、全く大丈夫そうではなかった。
そのすぐあとに大橋さんが最初に呼ばれていったので「がんばってくださいね!」と言って見送った。
大橋さんは、ベッドごと運ばれていった。ベッドで移動できるなんてファンタジー映画みたいだけど、そのまま手術室へ運ばれ、手術台に横付けしてまな板の上にゴロンと転がされる。帰りは逆の手順で戻ってくるというわけだ。下半身麻酔をした患者を運ぶ、最も効率的な方法だ。
ということは、僕はほぼ手術台の上に座っているようなものだった。このベッドの上でこれから起こるであろう惨状に震える思いがした。
二十分後、大橋さんを乗せたベッドが戻ってきた。看護師さんが「はい~終わりましたっ!」と言ってベッドを元の位置に固定した。「はい~パン焼けましたっ!」みたいなカジュアルな言い方にちょっと腹が立った。
手術直後の人というものを初めて見る。大橋さんは宙を見つめて「あ~」とずっと言っている。僕もこうなってしまうのか。
「ど、どうだってんですか大橋さん!」
「あ~やべ~」
「何が、何がやばかったっすか!」
「切った痔を見せてくるサービスいらね~」
先発の大橋さんは何の参考にもならなかった。結局二番手は僕で、全容が掴めぬまま、僕のベッドは手術室を目指した。
手術室には院長と、その後ろに研修医が十人くらい居た。ぼくのお尻の見学者が多すぎないか? と思った。
「はいはい、すぐやっちゃうからね。パパッ! とね、ハハッ。というわけで楽にして、ホイ、じゃあまず、そこに座って頂こうかな」
ドラマのような仰々しい手術室のやりとりが始まったら緊張してしまうなと思っていたので、院長のインチキ手品師のような対応が返って有り難かった。
そういえば、院長の顔を見たのは実に半年ぶりである。本当に僕の症状を把握しているのか心配になったけれど、それはさすがに前日の検査のカルテを見ていたようで、
「ちょっと奥にあるから難しいんだけど、取っちゃうからね。膿の袋は取り残すと再発することがあるんで、ちょっと多めに患部を取ります。あ、でもまあ、すごく小さく取るから」
多いのか小さいのか分からなかったけど、きっと多めに取るんだろう。怖い感じになったので言い直してくれたのはきっと優しさだ。
僕としてはもう、腰椎麻酔で肛門をガッと広げる、という第一関門の時点で怖さの臨界点を超えていたので、そのあとは何だってよかったのだけど。
「ホイ、では麻酔を打つので、ここに座って、頭を低くしていただいて」
遂に来た。もうどうにでもなれ、と思ったが、やはり足が震える。「あーもうーあーやだなー」という小さい声が思わず漏れる。
「緊張してるね。でもねえ、大丈夫だからね、ねえ、村田先生」
「は、はい」
院長からでかい注射器を受け取った村田先生は明らかに僕より緊張していた。えっ研修医が打つのか。それは聞いてない。腰椎の周りには大事な神経がいっぱいあるんじゃないのか。大丈夫なんだろうな。いや研修医に罪はない。誰だって初めてがある。でも僕じゃなくて良くないか。はじめて同士のセックスが笑い話になるように、はじめて同士の医者と患者は笑える状況にならないか。いや笑えない。まじか。
僕より緊張してる村田先生が、肋骨をなぞり始める。
「ここ……」
「そう、そこだ。ドンと、力入れないとダメだからね、自信を持って」
これは人生最大のピンチかもしれないと思った。頭の中で般若心経を唱える。色即是空。僕は空の概念が好きだ。仏教をちゃんと学んだわけではないので合っているか知らないけど、この世は空だというのはすごく分かる気がする。なんでもあるし、なにもない、と思うとしっくりくることが多い。そう、なにもないのだ。関係だけがある。村田先生と注射と僕の関係だけが、たまたまそこに出現する。そしてすぐに消えていくのだ。ドン。
ドンが来た。足を動かしてみる。まだ動く。あれ?
「あれ?」
あれ? を先に村田先生に言われてしまった。
「もうちょっと、こういう感じかな! 大丈夫! いちに、さん!」
院長のインチキ手品師の仕草が急に不安になる。大丈夫だ。色即是空。この世界には、なにもないのだ。関係だけがある。村田先生と注射と僕の関係だけが、たまたまそこに出現する。そしてすぐに消えていくのだ。ドン。
「あれ?」
村田先生全然消えてくれない。ずっと僕の後ろに居るじゃん。お釈迦様よ、これが「縁」なのか?
最終的に院長が麻酔をしてくれて、数秒で足がじんわり痺れてきた。下半身が一切言うことを聞かない物質と化した。なるほど、こういう感じか。死の感覚とかもこの延長にあるものだろうか。
身体の自由が利かない僕を、看護士が四つん這いにさせた。そのあとのことは実はあまり覚えていない。後ろからカチャカチャと器具の音だけがせわしなく聞こえてきたが、感覚が無いので何をされているのかさっぱり分からなかった。それで、あとはどうにでもなれという気持ちになったのだった。
最後に院長が白い膿の塊を見せてくれて「あっこれは知ってる情報!」と思った。
帰りのベッドは、麻酔が効いているからかおしりに伝わる揺れが軽減されていて、僕はいつか乗ったベンツの座り心地を思い返していた。
その後熊田さんも手術を終え、僕たちの病室は安堵に包まれた。
朝と違うのは、下半身が動かないことだけだった。足の指を動かそうと必死で指令を出すも、どこかでたち消えてしまう。今まで出来ていたことが奇跡のように思えてくる。本当に出来ていたっけ? 指令の出し方が怪しくなってきたので上半身でおさらいする。大丈夫だ、手は素早く動く。確認するように、僕は寝ながらしばらく手刀を振り回した。隣のベッドから似たような風を切る音が聞こえてきたのでやめた。
ところで下半身麻酔の「下半身」の境界はどこなのか。腹をつねってみると、なんとなく感覚がある。膀胱あたりから怪しくなる。ふとパンツの中を見ると、丸まって冬眠をするリスみたいなのが居た。リスを起こさないようにそうっと撫でてみる。すやすや寝ていた。撫でられている感覚は無く、本当に自分ではない生命を愛でているようだった。これは確かにおしっこは無理そうだ。麻酔が切れるのは、夜の六時頃だろうか。僕はしばらく眠ることにした。
しきりに呼ばれている気がして目が覚めた。時計を見ると午後四時だ。うまいこと寝て時間が潰せた。早ければそろそろ麻酔か切れる頃だけど、太ももをつねっても痛くない。足の指もまだ動かなかった。
呼んでいたのは、隣の大橋さんだった。
「ねえ、おしっこ行きたくない?」
「いや、行きたくないですね」
僕は朝から水を一滴も飲んでいないし、念には念を入れて、手術前に最後の残りを出し切ったのだ。
「えーっ? 俺すっごい行きたいんだけど」
それはそうだろう。あなたはそういうことを朝やっていた。
「本当に僕行きたくないんですよ。あと2時間だからがんばりましょうよ」
「駄目だ。看護師さん呼ぶわ」
せっかく励ましたのに諦めるのがとてつもなく早くて驚いた。
案の定、看護師さんにも励まされていたが、大橋さんはもう我慢できないの一点張りだった。看護師さんはしぶしぶカテーテルを取りに行った。
「一緒にカテーテルやんない?」
「やらないですね絶対にやらないですね」
連れションならぬ連れカテーテルのお誘いなんて、もう一生受けることはないだろう。それよりも、点滴で水分を摂取しているせいか僕の膀胱も安泰というわけではないことに気付いた。半分以上は溜まっているかもしれない。連れションだったら行くレベルだ。怖い怖い。カテーテル怖い。あと二時間、大事を取って寝てしまうのが一番安全だ。僕は布団を被り、目を閉じた。寝てしまうんだ。あわよくば寝汗で水を消費するんだ。
しかし隣から聞こえてくる大橋さんの絶叫と「ジョボボボ……」という音で完全に覚醒してしまい、そのあとの時間を僕は不安に押しつぶされそうになりながら過ごした。
待ちに待った足の感覚は午後五時頃に突然戻ってきた。感覚のタイツを履いていくような感じがした。履いたところからあっという間に生き返って、満ちていく。
最初のトイレは、足に残った麻酔で倒れる危険があるので看護師が付いていく決まりになっていた。おしっこが出ると、看護師がほめてくれた。おしっこで褒められたのは何十年ぶりだろう。いや、大げさでなく、おしっこで力める力が戻ってきていることの確認、これが手術後に提示されたいくつかの回復目標の一番目なのだった。
大橋さんが放尿に成功したのは深夜だった。