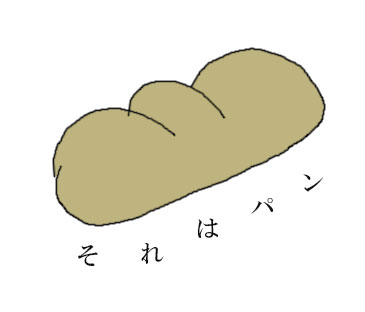手術着に着替えて「2」という部屋に入った。今日は手術以外は「2」という部屋を使えるらしい。なぜ本日一番目なのに「2」なのかは聞かなかった。「2」という部屋に、本やイヤホンを持ち込んで良いと言われた。直後にそんなに寛げるものかね……と訝しんだけれど、局部麻酔が効いているので逆に元気らしい(なにしろ歩いて帰れるのだ)。そとのきちょうど鞄に入っていたのが「ハプスブルク帝国」という、ハプスブルク家の歴史を詳細に解説した新書だった。手術後にちっとも読みたくない本の一つだ。でもそれしか持っていなかったのでそれを「2」に持ち込んだ。
そのあとすぐに「麻酔科の先生」が入ってきて、今日の麻酔の説明をする。
「おくすりがはいりますと すぐにねむたくなります そうしてねてしまいますと しゅじゅつはおわっています」
麻酔の先生は1日3回(手術枠は1日に3枠だから)、数年間同じ説明をしてきたからだろう、麻酔の説明が完全に「台詞」に昇華されていた。目は僕を見ているようで見ておらずやや上を向き、麻酔の効能を高らかに、淀みなく歌い上げていた。それでいて文節と文節の間に絶妙な間があり、高尚な詩を聞いているようでもあった。
これは教会の神父だと思った。「やめるときも すこやかなるときも」のあれだ。思えば麻酔とは人を仮死状態にするようなものだ。聖なる力であるところの麻酔を扱うのが神父であってもおかしくないと思った。彼は最後一瞬十字を切った気もする。そんなことを考えていたから、麻酔についての説明は全く耳に入ってこなかった。
神父が出て行くのと入れ替わりに看護師が現れ「それでは手術室へ行きましょう」と言う。あ、先生と話す隙は無いのだな、と思った。ちょっと待ってくれ。そういえば僕は本当に鼠径ヘルニアなのか、という疑問。クリアになったわけではない。このまま手術が始まってしまう。手術台に寝かされる。先生に聞いてみようか。先生はまだ現れないが、手術台の周りにはすでに4人ほどの看護師が僕に関する作業をするために自律的に動き回っていて、もはや止めるのが躊躇われるくらいの、いやでも、本当に鼠径ヘルニアでなかったらこれは後悔することになるし、カメラ入れてみて「あれー? 穴あいてないね?」とかそういうことになっても全員困るわけだ、彼らはもう職務を全うすることしか考えておらず、そのような疑いは一切持っていないだろうからここは一番冷静な僕が「ところで、僕は本当に鼠径ヘルニアなんですか?」と確認したほうがいいだろう、サンクコスト効果、中止して引き返すときに回収できない損失を恐れて突き進んでしまうことを言うのだけど、こういうのもきっとそうで、迷惑がかかるから言わないでおく、というのが最終的に一番迷惑なのだから、僕が鼠径ヘルニアではないかもしれない、というのは一応言ったほうが良くて、「それでは おくすりを いれていきます はい もうはいりましたよ」出たな神父め「だんだん ねむくなっていきます」うわ、もうやるんだ、なるほど、このバタバタ感は患者に考える隙をあたえないための、薬が入ってくるの分かるもんだね、これはダメか、1、2、3、まだ分かる、数えていて、ぼうっと白くなって、起きたら「2」の部屋に居た。
「はい いまはじゅうじさんじっぷんです ゆめをみていましたか?」
もう思い出せないけれど、確かに夢を見ていた。何か寝言でも言ってたんだろうか。全身麻酔をやった人のブログをいっぱい読んでいて、みんな「時間が吹き飛ぶ」みたいなことを言っていた。意識と時間は関係があるのだろう。意識のハードスイッチを切ったとき、もしかしたら時間は吹き飛ぶのかもしれないと想像していた。自我の起動、時間感覚の起動に立ち会うチャンスかもしれない、など思っていたのに、ふつうに1時間30分くらい寝た感覚があった。日曜の午前を残念に過ごしたときのあの感じと全く一緒。全身麻酔、ふつうだ……つまらないぞ、全身麻酔。
ちなみに、僕の次に手術を受けたであろう人は隣の「3」の部屋に居て、僕がだらだらしているうちに手術室から帰ってきたのだけど、神父の声が漏れ聞こえてきて「はい いまは じゅうにじちょうどです いっしゅんでしたか?」と言っていた。神父は状況によって台詞を変えているようだった。深い眠りに入る人も居るのかもしれない。彼は時間が消えたのだろうか。
腹を見ると、へそと下腹部の2箇所、合計3箇所に防水の絆創膏のようなものが貼られていた。傷としてはそれだけで、お腹に力を入れると確かに少し痛いのだけど、動けないことは全くなかった。看護師によると「局部麻酔も効いていますからしばらくは痛みも少ないと思います」とのことだった。本当に、すべてが終わったのか? 達成感が少しもない。寝ていただけだからだ。これが二十一世紀の医学の到達点か、と畏怖の念を覚えた。これは魔法だ。小さい頃に大きな手術をして医者を目指す子供の気持ちが少し分かる。暇になったので持ってきた本に手を伸ばした。ハプスブルク家の興隆を詳細に解説したそれは案の定、いまの気分と全く合わなかった。