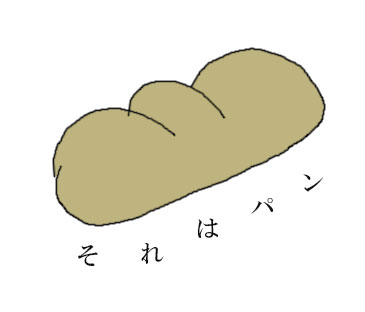ところで、麻酔が切れたということは、手術跡の痛みを直接感じるということでもあった。そのうち、五寸釘をコーン! コーン! と打ち続けているような痛みの波が襲ってきた。それはまだ良いほうで、ちょっとでも体を動かそうものなら五寸釘の周期は突然コンコンコンコンコン! とトランス状態になって収拾がつかなくなる。肛門を怒らせないように、ベッドにうつ伏せになって凌いだ。
とはいえ、かつて痔瘻の膿が破裂する直前に感じた絶望的な痛みに比べたら大したことない気がしたし、我慢しがいのあるものだった。手術後のそれは必ず収まることが保証された、希望の持てる痛みだった。
しかし夜は自律神経のバランスからか、痛みが五割増しになって襲ってくる。
それで、隣の大橋さんのベッドから、カーテン越しに諦めの声が聞こえるのだった。
「もう駄目だ~。帰りて~。あ~」
「大丈夫ですか?」
「あ~。帰りて~」
家に帰ってどうこうなるものでもないと思うが、こういうときの家信奉ってあるよな、と思った。僕は眠かったので、さっさと寝てしまったけれど、どうやら大橋さんはずっと声を出していたらしかった。本人が翌日そう言っていたのだ。
「昨日はほんと申し訳ない。ずっと呻いていて」
「いや大丈夫です、僕はわりと煩くても寝られるので。それより大丈夫ですか?」
「四個取ったからかな~みんなの四倍痛いのかもしれない」
みんなの四倍かどうかは分からないが、これはもっともだ。患部の数だけ痛いだろう。
「俺さあ、多分今夜もずっと煩いと思うんだよね、だから個室が空いてたら移ろうと思うんだ」
「えっ僕は全然気にしてないですよ」
「俺も大丈夫だよ、そんなのに気を遣うなって」と熊田さん。
「いや、でもさあ、迷惑を掛けちゃうからさあ……申し訳ないよ……」
大橋さんは自分には全く気を遣わないが、人にはめちゃくちゃ気を遣うようだった。このままでは大橋さんは本当に個室へ行ってしまいそうだった。僕はもう既に、大橋さんを失ったらこの入院の意味は終わるとさえ思っていた。
「何言ってるんすか! 僕ら、痛い仲間じゃないですか!」
独りで熱くなってしまった。なんかもうちょっと言い方があった気がするが、とっさに出たのが「痛い仲間」というワードだった。
僕はこのとき、この病院生活は部活動だと確信した。同じ日に入部し、同じ回復目標を突破していく仲間。誰も欠けることなく、ゴールするのだ。書道部の僕がそう思うのだから、ラグビー部の熊田さんもきっと同じ気持ちだ。
「まあでも、個室に行きますわ……煩いし……」
僕の言葉は大橋さんに全然響いていなかった。この人はいったい何部だったんだろうか。
定期巡回してきた看護師さんに個室の相談をする大橋さんに、僕はこれ以上かける言葉が見つからなかった。
「あー今ねえ、個室空いてないのよ。ずーっといっぱい」
商売上手の肛門クリニックが、個室を空けておくわけがなかった。大橋さんの残留が確定した。
次の日の夜も大橋さんは痛そうだった。ナースコールを頻繁に押して「痛いんですけど……」と訴えていたが、この病院にはロキソニンしか手段はないらしく、看護師さんから「みんなも頑張ってるからねえ」みたいなしょうもない精神論で諭されていた。普通の人ならそこで諦めると思うのだけど、大橋さんはまたナースコールを押すのだった。そのうち看護師さんもちょっとイライラしてきて
「痛いのは当たり前だから! 私を呼んでも何もないから!」
と、ぶっちゃけてしまった。これが大橋さんにはかなり堪えたらしく「あんな言い方はない。俺はここを出ていく」と、翌日に荷物をまとめ始めた。本当に出て行きそうでまずいなと思っていたんだけど、そこにちょうど、大橋さんのお父さんが見舞いにやってきたのだった。当時はコロナ騒動前だったので、日中であれば自由にお見舞いが出来る良い時代だった。
大橋さんのお父さんはけっこうお年を召していて、入れ歯のせいか訛りのせいかは分からないけれど、フガフガと喋る感じの方だった。ご挨拶いただいて「息子が世話になってますね」だけは聞き取れたが、それ以降は分からなかったので僕は愛想笑いで「ええ、ええ」と頷いた。
カーテンの向こうから、ものすごく怒っている大橋さんの「もう帰りてえよ俺は!」という声が聞こえる。お父さんは、それに対してフガフガと返していた。
「いやだからさあ! 看護師がダメなんだよ。痛いってのになんもしてくれないの!」
「フガフガ、フガ、フガガ」
「それだったら帰っても一緒じゃない?」
「フガ、フガガ、フガ」
「うーん、まあ……もうちょっと居るわ……」
どうやったかは全く分からなかったが、説得に成功した。
大橋さんのお父さんは、病室のみんなに小麦まんじゅうを配って帰っていった。ただ僕たちは絶食中だったので、味わえるのはもう少し先だった。枕元に置いて、眺めて過ごした。